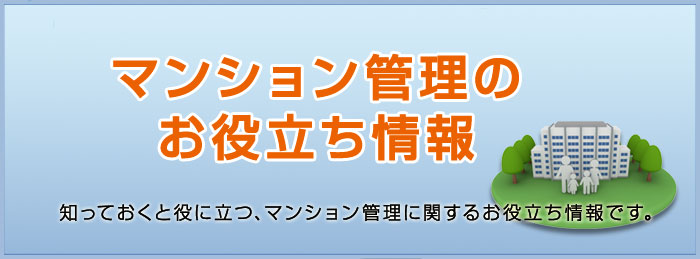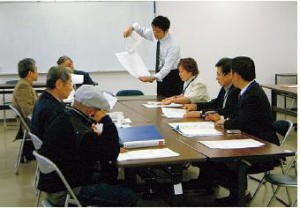理事会役員のなり手不足を解消するには
昨今、マンションでの理事会役員のなり手不足は深刻化しており
弊社で管理させていただいているマンションも例外ではありません。
マンションの築年数の経過に伴い居住者も高齢化し、体力的に難しい方や
若くても仕事で忙しい方
単純にマンションの維持管理に無関心である方などの増加により
輪番制で役員が回ってきても欠席ばかりで
実質役員業務をしていない人が増えました。
特に出来るけどやらない「無関心層」の増加は深刻です。
以前、私が担当しているマンションで
欠席者が抽選で理事長に就任したことがあり
本人にそれをお伝えしたところ
「忙しいのでやらない」と一方的に断られてしまったこともありました。
管理会社は理事長を選任する立場になく
あくまでも決定事項をお伝えするだけですので
こういった場合、対処が非常に難しいです。
結局、その時は別の役員様に事情をお伝えして理事長に就任いただきましたが
マンションの維持管理にご理解のある方に負担が集中してしまっている現状は
やはり好ましくないと思います。
以前のブログで役員の負担を減らすための方法として
第三者管理者方式をご紹介しましたが
それなりの費用が掛かるので実際依頼できる管理組合は多くないと思います。
今回は、なるべく費用を掛けずに
役員のなり手を誘致する方法を考えてみたいと思います。
役員を誘致するには、仕事を理解してもらうことと
参加しやすくする環境が大事だと思います。
あくまでも一例ですが、理事会の改善点を考えてみました。
役員の業務は明確であるか?
役員をしたくない理由の一つに
「何をしたらいいか判らない」いう方がいると思います。
どのような仕事があるのか、生活にどのくらいの負担になるのか
といった不安要素があり
役員の就任を嫌う傾向があるようです。
役員になった場合、どのような仕事をおこなうか明確化することにより
「思ったより難しくないな」とか
「これくらいの負担で自分のマンションを守る為なら」といった
意識の方を役員に誘致することができます。
管理会社に業務委託しているマンションでは
役員業務は大きく軽減されていると思いますので
まずはそれを知ってもらうことが大事だと思います。
無駄な理事会をしていないか?
マンションによっては月に1回程度
必ず定例で理事会を開催している所もありますが
定例なので検討する事項がない時でも開催されるので
ほぼ雑談だけで協議が終わってしまう場合も少なくありません。
人によってはこの雑談の時間が無駄に感じることがあり
建設的でないなら参加しないといった考えの方もいます。
定例の理事会は廃止して
協議の必要な事項が出来た時に都度理事会を開催するようにすれば
開催の頻度を減らせますし、雑談も減ります。
効率的な理事会を開催することにより
「効率的に理事会に参加したい」といった人を誘致できます。
役員数は適正か?
役員の人数は、マンション毎に管理規約に定められています。
極端に役員が多い場合には管理規約を改正して
役員の定数を減らすことも有効な方法です。
役員の適正な人数は一概にはいえませんが
管理会社に業務委託している一般的なマンションでは
役員の人数があまり多くないほうが
速やかな理事会運営となることが多いようです。
役員資格の拡大
法令上は役員の資格についての制限はないため
管理規約を改定することにより
役員の資格要件を拡大することができます。
多くの管理組合では役員の資格については
管理規約では区分所有者であることを要件としています。
理事のなり手を確保するという目的であればこうした要件を廃止し
配偶者や親族等もOKにすれば
高齢の区分所有者でもご自分の代わりをたてられますので有効です。
しかし、区分所有者以外の例えば賃借人等が役員になった場合には
区分所有者の利益に反する方向に
話が進んでしまう可能性もあり得ますので
資格の拡大範囲は慎重に検討しましょう。
役員のなり手不足が悪化すると
マンションの維持管理ができなくなり
結果的に資産価値の低下、最悪の場合スラム化につながります。
抜本的な解決方法はありませんが
区分所有者が少しでも役員に参加しやすくする環境を整えることが大事だと思います。
理事長の仕事とは
理事会の役員が輪番制になっている管理組合は多いと思いますが
その場合、抽選等により思いもよらず理事長になってしまうといったケースもあります。
いままで理事会・総会にあまり参加してこなかった方は
理事長がどのようなことをしているのか見当もつかないと思いますが
実際どのようなことをしているのでしょうか。
今回は、管理会社と管理委託契約を結んでいるマンションで
理事長がどのような仕事をしているか、ご紹介したいと思います。
・重要書類の引継ぎ・保管
前任の理事長から管理組合の重要書類を引継ぎ、保管します。
点検・修繕の報告書や会議の際に使用した資料などの多くは
管理室や管理会社で保管できますが
管理会社で保管することが好ましくない書類(例えば管理会社との契約書など)は
理事長が保管します。
・銀行印の引継ぎ・保管
管理組合は、区分所有者から管理費や修繕積立金などを徴収したり
各種費用を支払う業務を行うため
銀行をはじめとする金融機関に預金口座を開設しています。
理事長が変更になりましたら
前任の理事長からこの預金口座の銀行印を引継ぎ、保管します。
預金の口座の通帳を管理会社で保管し
銀行印を理事長が保管し分別管理することで
不明な出金を防ぐ狙いがあります。
各種費用の支払いが発生した場合
管理会社は金融機関の振込書類を作成し
理事長に捺印いただくことで、支払いを行います。
・預金口座の名義変更
通常、ほとんどの管理組合は法人化していないため
法人格のない団体となり
預金口座は「○○マンション管理組合 理事長〇〇 〇〇」という名義で
各種取り引きを行うことになります。
理事長が変更となりましたら
預金口座の名義を今の理事長の名義に変更する手続きを
金融機関にて行います。
身分証明書以外の必要な書類は管理会社が準備してくれます。
・月次収支報告書の確認
管理会社は毎月、「月次収支報告書」を作成し
管理組合に報告しなければなりません。
これは「マンション管理適正化法」という法律で義務付けられており
管理会社はその月の収支報告書を管理費会計、修繕積立金会計と区別して作成し
1ヶ月以内に書面で管理組合の管理者(理事長)等に交付しなければなりません。
月次報告書に添付されている資料は管理会社によって異なりますが
一般的には貸借対照表、未収金一覧表等も添付します。
理事長は毎月月次報告書を確認し、管理組合の収支を把握します。
・理事会や総会の開催
理事会はその期の役員のみで行う会議で
総会は組合員全員で行う会議です。
マンションの修繕やトラブルの解決など
マンションを維持管理していくための会議を行います。
軽微な修繕やトラブルの解決などは理事会で決定することが多いですが
大きな修繕や決定事項などは、理事会で方針を決めて
年に1度の総会で議案として組合員に上程します。
理事会は年に数回開催し、総会は通常年に1度開催されます。
(緊急で決めたいことがある場合、臨時総会を開催する場合があります)
理事長は議長として、日時と議題を決めて会議の進行を行いますが
管理会社が代わりに進行を行うことも可能です。
・各種契約の締結
工事や点検、清掃を業者に依頼する際の契約や
共用部分の保険契約は、理事長が締結します。
・居住者からの相談やトラブル発生時の対応
居住者の方からの相談やマンションでトラブルが発生した時に
解決すべく対応します。
理事長本人に相談してくるケースもあれば
管理会社経由で相談があるケースもあります。
理事長ひとりで判断するのが難しい場合は
理事会で協議を行うか、管理会社に相談します。
上記はあくまでも一般的な業務ですので
管理組合によっては、別に特殊な仕事を行っている場合もあります。
仕事は多岐にわたり、最初は考えることが多く
負担に感じることもあるかもしれませんが
判らないことがあれば管理会社のフロントになんでも相談してみましょう。
理事長職を務めることは
ご自身のマンションを知る良い機会でもあります。
会議の議事録について
管理組合の会議の議事録には
決議の結果や参加者から出された意見などが記録されており
現在や過去のマンションの状況を知る上での大事なツールとなります。
マンションで行われる会議には、主に総会と理事会がありますが
組合員全体を出席対象とした総会については
区分所有法第42条第1項の規定により、議事録の作成が義務付けられています。
総会の議事録は、原則として議長を務める理事長が作成しますが
選任された理事などが議事録の作成をおこなう場合もあります。
但し、管理会社に管理を委託している場合
管理会社の担当者(フロントマン)が理事会に同席し
議事録の素案を作成していることが多いのが実状です。
議事録の作成には手間と時間がかかるため
管理会社に作成してもらうのは結構なことですが
作成者はあくまでも議長(理事長)であるため
議長は管理会社の作成した素案の内容をよく確認のうえで
署名、押印することが大切です。
議事録の書き方に決まりはなく
議事の内容をすべて記載する必要はありませんが
日時・出席者数・議案・決議結果などの要点を
正確に記載する必要はあります。
また、そのマンションごとにある程度書式を決めて作成したほうが
読む側(組合員)はより読みやすくなります。
議事録を全戸に配付するかどうかは
管理規約等に定められている場合のほか
各管理組合の慣例等により異なります。
弊社でも以前は議事録のコピーを全戸に配布しておりましたが
ペーパーレス化の観点から、紙での配布をなるべく控え
管理組合専用のポータルサイト上で議事録を確認頂くよう努めております。
近年は、時間がかかる、家の用事を優先したい等の理由で
総会の出席を委任する人が増えているように思えます。
いくら時間をかけて議論をかさねても
組合員に結果を伝え共有しなければトラブルにも繋がるため
議事録の作成・公開は大切です。
できる限り多くの組合員の目に留まる方法で
議事録を公開することが望ましいでしょう。
リモートで理事会・総会を開催するには
新型コロナウイルスによる影響も若干落ち着いてはきましたが、
弊社管理物件の一部では今も尚理事会の開催を見送ったり、
総会を書面決議で開催したりといった組合活動の自粛がございます。
そんな状況の世の中、注目されているのがITを活用した組合活動です。
令和3年6月の標準管理規約の改正においても、「ITを活用した理事会・総会」すなわち、
リモートでの理事会・総会の開催が可能であることが明確化され、
これにあわせて留意事項等が記載されました。
※標準管理規約とは、各管理組合がマンションの維持・管理や生活する上での
ルールを定めた管理規約を、作成・変更をする際の参考になるよう、
国土交通省が作成したものです。
管理組合がリモートでの理事会・総会を開催するためには、以下の準備が必要です。
管理規約の改正
まずは管理組合がリモートでの理事会・総会を開催可能であることを
あらかじめ管理規約に明記するために、規約を総会で改正しておく必要があります。
令和3年6月に改正した標準管理規約の第2条十及び十一、第38条コメント、
第43条及び同条コメント、第47条及び同条コメント、第52条コメント、
第53条及び同条コメントが参考になります。
IT環境の構築
リモートでの理事会・総会を開催するためには、以下のものが必要になります。
1.パソコン・スマートフォン・タブレット等の端末
2.インターネット回線
3.WEB会議アプリ
4.カメラ、音響機器、モニター等(リモートとリアル理事会・総会開催を併用する場合)
リアル理事会・総会とは、マンションの集会室や公民館等の会場で開催する
一般的な形式の理事会・総会を指します。
リモートでの理事会・総会はどこにいても参加できることが最大のメリットですが、
ITの使い方がわからない方や、Wi-Fi環境が無くインターネット接続料に
抵抗を感じる方もいらっしゃる可能性がありますので、現状では
リモートとリアルを併用する理事会・総会の開催が望ましいといえます。
今後さらに発展するIT技術の活用に向けて、
今から管理組合で少しずつ準備してみてはいかがでしょうか。
管理組合の決算報告・総会
マンション管理組合では、毎年3月を決算月としているところが多くあります。
総会開催を会計年度終了から2ヶ月以内と定めている管理組合は
一定数あるなか、現状多くの管理組合は、日程の都合により3ヶ月以内に
通常総会を開催しています。
※ 例として事業年度が4月~3月、6月を通常総会に想定したスケジュール
・決算報告書の種類
自主管理マンションの決算報告書に多く目にするのは、金銭の出入りをお小遣い帳の
様に収支報告のみで貸借対照表がない場合です。
これは、単式簿記(現金主義)と言って帳簿の書き方がシンプルであるため、報告内容も
簡単なものとなり、手元の現金がいくら増えたか、減ったかがわかる仕組みです。
しかし、単式簿記(現金主義)は、基本的に現金の増減を把握して帳簿を作成するため、
現金や借金等の残高がわからないことや、収支が必ずしも正しい期間に計上されない等、
財政状態の把握が曖昧という問題点があります。
また、管理費等の収入を現金の入金時点で計上するため、納入していない管理費等に
未収金が発生しても、決算書のどこにも計上されません。
管理組合会計は、複式簿記(発生主義)で行うのが一般的で、管理費等の収入がどこの
預金口座に入金されたのか、現金で保有しているのか記録されることになります。
毎月の管理費等の収入は入金があった分だけではなく、入金がなかった分についても
未収金として計上します。
翌月分の管理費等を入金された場合は、前受金となり、貸借対照表にも計上されます。
管理費等収入は、その期に入金された収入だけでなく、未収金分の収入も含まれるため、
前受金や未収金を管理費等に振替える必要があり、貸借対照表に未収金として計上された
管理費等は支払が完了するまで残高が残りますので、決算書を見れば、滞納状況も把握
できるということです。
あるべき収入が計上され、納入されていない管理費等があるか、未収金の残高により
読み取ることが出来ます。
・区分管理をしていない
管理費会計と修繕積立金会計にわけて使い道をしっかり把握します。
毎月管理費等はマンションの建物等を管理するために集め、管理費等の収入を入金段階
から管理費会計と修繕積立金会計に区分し目的に分けて決算する必要があります。
共用設備の保守点検費、管理員人件費、組合運営、消耗品費等の経費は管理費会計に
充当します。
また、修繕積立金は計画的に行われる大規模修繕工事費や計画的修繕等、特別な費用を
修繕積立金会計に充当します。
日常的な維持管理のために必要となる管理費会計と将来必要となる修繕積立金会計に
別に確保しておくことが、財政状態を保つためには必要となります。
例えば管理組合の運営にあたり、管理費会計の支出が膨らんで修繕積立金を取り崩して
しまうようなことは、将来の大規模修繕工事や設備の取替が必要になった場合、どうやって
捻出するか大きな問題となってしまう危険性があるからです。
最後に、決算報告は管理組合に収めた管理費等がきちんと目的通りに使われたか、
今年一年に必要だった支出に対して充足していたのか不足していたのか、
現在の財産がどれだけあるのか、
修繕積立金は予定通り積み立てられているのか、
決められた通り管理費等を納入しているか等を、
知ることができる報告となり、
毎月の管理費等の支払いが目的通り正しく使われているか、
その結果が決算報告となり、
その報告を行うのが通常総会となるのです。
自主管理マンション 自主管理 限界マンション 総会 怖い
マンション 総会 議案
マンション 理事会 議案書
マンション 議案書 作成
マンション 総会 議案書 書き方