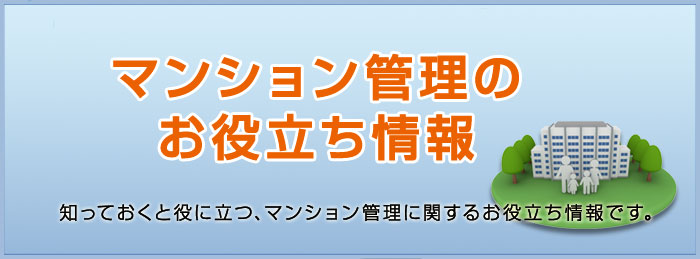マンションの給水方式について
皆様がお住まいのマンションで
緊急時以外に断水することはありますでしょうか?
マンションごとに水を供給する方法は違っているので
停電や水道本管の断水などの緊急時だけでなく
設備のメンテナンスにより
計画的に水が使用出来なくなるマンションもあります。
では実際に、マンションでは
どのような給水方式が採用されているのでしょうか。
マンションの給水方式には大きく分けて
「受水槽給水方式」、「高架水槽給水方式」、「増圧直結給水方式」、「直圧直結給水方式」の
4つの方式があります。
受水槽給水方式
水道本管から受水槽に供給した水を
加圧ポンプを利用して各戸に供給する方式で
中小規模のマンションで主流になっている給水方式です。
メリットとしては
停電や水道本管の断水時も
受水槽内の水を利用することがあげられます。
但し、停電等の理由によりポンプが止まっている場合は
各戸に個別給水することが出来なくなるため
受水槽からの直接水を汲み出す必要があります。
デメリットとしては
受水槽の清掃費用や検査費用が掛かることです。

高架水槽給水方式
水道本管から1階受水槽に一旦水を給水し
そこから揚水ポンプを利用して
屋上の小さな高架水槽へ水を揚水し
重力を利用して各戸へ水を供給する方式です。
以前は多くのマンションで採用されてきた方式ですが
近年は給水ポンプの性能向上により
あまり見かけなくなりました。
メリットとしては
停電や水道本管の断水時も
受水槽内の水を利用することが出来ます。
また、この方式は水の重力を利用して各戸へ給水するので
停電でポンプが停止した状態でも
高架水槽の分の水は蛇口から給水可能です。
デメリットは
重力で水を供給するため低層階だと水圧が高いですが
上階だと水圧が低くなってしまいます。
また、受水槽にプラスして
高架水槽の清掃費用や検査費用が別途掛かります。
増圧直結給水方式
水道本管内の給水圧に加えて
更に増圧ポンプで水圧を高めて
受水槽などを経由せずに本管から直接各戸に給水する方式です。
近年の新築マンションでは
この給水方式が多く見受けられます。
メリットとしては
受水槽や高架水槽に水を貯めないので衛生的です。
また、水槽の清掃費用や検査費用は掛かりません。
(増圧ポンプの法定点検費用は掛かります)
デメリットとしては
停電時には上階への給水圧力が低下するので
即時に断水することです。
また、圧力の関係から
概ね15階程度のマンションが限界とされています。
直圧直結給水方式
水道本管内の給水圧のみで直接各戸に給水する方式です。
メリットとしては
水槽に水を貯めないで衛生的であること
水槽やポンプを設置しないので
給水管以外の設備の維持管理費が掛からないこと
停電時でも給水可能であること等
他の給水方式より大きなメリットがあります。
但し、デメリットといえるかわかりませんが
直結直圧給水方式が可能なマンションは
水圧の関係で都市部の低層マンションに限られています。
※詳しくは各自治体にご確認ください。
ご自身のマンションで
どのような給水方式が採用されているか判ると
緊急時への備えの意識も変わってくると思います。
特に受水槽給水方式や増圧直結給水方式を採用していると
停電が起きただけで
水も出なくなってしまうことになりますので
飲み水や生活用水の確保など
日頃からの備えをお勧めします。
第三者管理方式とは
昨今、管理組合で深刻な問題となっているのが役員のなり手不足です。
分譲マンションでは築年数の経過に伴い
今まで役員を担ってきた方たちの高齢化が進み
役員業務を行うことが困難になってきたり
共働き夫婦の増加により
役員業務に時間を割くことが難しくなったなどの理由で
役員の就任を辞退するケースも多いようです。
実際、役員業務を積極的に行うとなると
時間に余裕があり、ある程度の体力がある人でなければ難しく
その様な人は限られてくると思います。
そうした問題を受け、国土交通省は2016年に
「標準管理規約」の見直しを行い
所有者以外の外部の専門家を管理者として選任する方法
つまり管理組合が管理者業務を
第三者(管理会社など)に委託する方式が条文で追加されており
大手の管理会社では第三者管理を引き受けているところもあるようです。
※現段階では弊社は第三者管理をお受けしておりません。

第三者管理方式には、基本的に以下の3つのパターンがあります。
1.第三者が管理者兼理事長に就任(理事会あり)
2.第三者が管理者に就任、区分所有者が理事長に就任(理事会あり)
3.第三者が管理者に就任、理事長はいない(理事会なし)
このうち3は、日常的な修繕や居住者間のトラブルの解決など
管理業務のほぼ全権を第三者にお任せする方式となり
区分所有者の負担は大きく軽減されます。
但し、以下のデメリットが考えられます。
①通常の管理委託契約とは別契約となり、現在の委託費にプラスして高額な費用が掛かる。
②工事などで管理会社に都合がいい業者を選定するおそれがある。利益相反のおそれがある。
③理事会はなくても、区分所有者から監事を選任する必要がある。
①についてはいわずもがな
管理会社が理事会の負担を一手に担うことになりますので
それなりの費用が掛かると考えられます。
②については、理事会(理事長)の承認を得ずに工事を発注できるため
相場よりも高額な工事費用が掛かる恐れがあり
それを防ぐためには事前に厳格なルールを定めなくてはなりません。
たとえば、大規模修繕工事の発注先を選定する際などにも
相見積もりの取得基準を設けたり
管理者の自社もしくは自社グループに対する発注ルールなどを
明確化しておく必要があります。
大規模修繕工事などの高額な費用が掛かる工事では
検討委員会を設けた方が良いでしょう。
③については、管理者を監視する立場として
区分所有者から監事を選任する必要があります。
結果的に、監事が今までの理事長のような責任的立場になると考えられます。
このように、第三者方式の3には
区分所有者の負担を大きく軽減できる一方
費用の問題であったり、信頼性の問題であったりなど
様々なデメリットもあり一長一短です。
管理会社に依頼する場合は、システムをよく理解した上で
理事会で充分な検討を重ねてからにしましょう。
個人賠償責任保険について
マンションのオーナーとなった際に
ほとんどの方が火災保険の加入を検討されるかと思いますが
火災保険と併せて付保しておきたい保険が
「個人賠償責任保険」です。
「個人賠償責任保険」とは
自動車事故以外の日常生活の事故により
他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまい
法律上の損害賠償責任を負った場合に補償が受けられるものですが
この保険、マンションにはつきものである漏水事故にも対応しています。
マンションで漏水事故が発生した場合
被害に遭われた下階のお部屋を原状回復する必要がありますが
この費用は漏水発生元である上階オーナー(または居住者)が
全額負担しなければなりません。
その際、「個人賠償責任保険」を付保していれば
この費用の一部または全額が補償の対象となり
上階オーナーの負担軽減が見込めます。
下階の原状回復費用は被害の状況によってまちまちですが
なかにはかなり高額な請求となるケースもあります。
例として、私が直近でご対応させていただいた
漏水事故3件の下階の原状回復費用をあげますと
・Aマンション 663,300円(天井ボード交換、クロス貼替、フローリング貼替)
・Bマンション 316,250円(天井ボード交換、クロス貼替、照明器具交換)
・Cマンション 1,370,600円(天井・壁ボード交換、クロス貼替、フローリング貼替)
※いずれも税込み
個人でお支払いするにはかなりの負担ではないでしょうか。
管理組合でも共用部分で付保している
「マンション総合保険」の特約としてこの保険が付いていることがあり
その場合、マンション内の漏水事故であれば
どのお部屋でも保険申請が可能ですが
近年の保険料値上げにより
この保険を付保しない管理組合も増えてきています。
ご自身のマンションでこの保険に加入しているか
一度ご確認をお勧めします。
もし管理組合でこの保険を付保していない場合は
ご自身の火災保険に「個人賠償責任特約」が
付保されているか確認してみてください。
(保険会社によっては「日常生活賠償責任特約」だったりと名称は様々です)
火災保険以外でも
例えば自動車(じどうしゃ)保険に付いているケースもあります。
自転車(じてんしゃ)保険でしたら
それだけで「個人賠償責任保険」と同じ補償が受けられますので
新たに付保する必要はありません。
いずれの保険にもない場合は付保を検討してみてください。
月額にすると数百円程度の負担で付保出来るところがほとんどですので
もしもの備えとしては高額ではないと思います。
漏水事故はいつ発生するかわかりません。
突然高額な費用を請求をされる前に、備えておきましょう。
大規模修繕工事とは
マンションを適切に維持管理していく上で重要な「大規模修繕工事」
理事会役員や修繕検討委員にならないと
どのような工事をおこなっているかなかなか分かりづらいと思います。
※修繕検討委員とは、大規模修繕に関する計画や決定事項などを
専門に行う委員会のメンバーのことです。
国土交通省のガイドラインでは、大規模修繕工事は
「マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するために行う修繕工事や
必要に応じて建物及び設備の性能向上を図るために行う改修工事のうち
工事内容が大規模、工事費が高額、工事期間が長期間にわたるもの等をいう。」
と書かれており、大体12年~15年に一度行うのが望ましいとされています。
具体的には、屋上やバルコニーの防水工事
外壁の下地補修・タイルの貼り替え・塗装、鉄部の塗装
シーリングの打ち替え等行い
場合によっては給水管や排水管の更新を行う場合もあります。
但し、工事内容はあくまでも管理組合が決めることであるため
必ずしもこの内容で行うとは限りません。
例えば屋上防水工事は足場を必要としないため
防水の状態が良好であれば、実施時期を延期することもあります。

大規模修繕工事を行うにあたり
理事会役員や修繕検討委員は次のようなことを行っています。
①建物の劣化状況を調べる
②劣化状況を基に、工事の内容を決める
③決めた工事内容で、(複数の)業者から見積りをとる
④見積りを基にどの業者に依頼するか決める
⑤工事内容、業者を決めたら総会に上程する
※上程とは、議案などを会議にかけることです
⑥総会にて可決承認後、業者と契約し、具体的な工事の日取りを決める
⑦工事中、追加で必要な工事が発生した場合、都度検討する
⑧工事が概ね終了したら、検査を行う
⑨検査終了後、業者から提出される工事完了報告書を確認し、工事終了
工事費用は戸あたり100万円が目安とされていましたが
築年数によりやらなければいけない工事が大きく変わってくるので
一概にはいえません。
また、最近は物価高騰のあおりを受け、工事金額が跳ね上がっているため
予想より見積が高額になることが多いです。
資金不足により工事が延期とならないように
管理組合は普段から修繕積立金を計画的に貯めていくことが重要です。
専用使用権について
マンションは「専有部分」とそれ以外の「共用部分」に分かれています。
「専有部分」はお部屋内、個人の所有(区分所有)となり、個人の財産です。
逆に「共用部分」はマンションの区分所有者全員の所有となり
共有の財産となる部分のことを言いますが
共用部分には専用使用権が付与された「専用使用部分」というものが存在します。
「専用使用部分」は特定の所有者が排他的に使用できる部分のことで
代表的なのは「バルコニー」。
仕切りで覆われていてそのお部屋の居住者しか使用しないため
感覚としては個人の所有に思えますが
区分所有者全員の所有となる「共用部分」であると同時に
その人しか通常使用しない「専用使用部分」となります。
※緊急時は避難経路になることもあります。
バルコニーの他に、専用使用部分には次のようなものがあります。
玄関扉外側、インターホン、玄関ポーチ、室外機置場、窓ガラス(サッシ含む)
専用庭、駐車場、駐輪場、給排水管の一部など・・・
「お部屋の外」にあって、「その人しか使わない」部分と考えれば
「専用使用部分」かそうでないかの区別がつきやすいと思います。
「専用使用部分」は「共用部分」であることから
計画的に全体で修繕を行うことがありますが
通常の管理は専用使用権を有している人が行うことになるため
例えばインターホンの修理や庭の草むしり、集合ポストのダイヤル交換は
一般的に個人でおこなうことになります。
もちろん、管理組合でおこなうこともありますが
それは各管理組合の方針により異なります。
弊社で管理させて頂いているマンションでも
集合ポストのダイヤルが故障した時や、玄関ドアの建付けが悪くなった時などに
管理組合の方針により、管理組合の費用負担で修理しているところもあります。
但し、「専用使用部分」は取り扱い方法や使用頻度により劣化が異なってくる部分が多いので
基本的には個人で直すという認識でいて
壊れたら一応管理組合に相談してみるのが良いと思います。
また、玄関等一部の「専用使用部分」については
景観の観点から修理はいいが交換は不可としているところが多いと思います。
後にトラブルにならないように、こちらも事前に管理組合に確認しましょう。